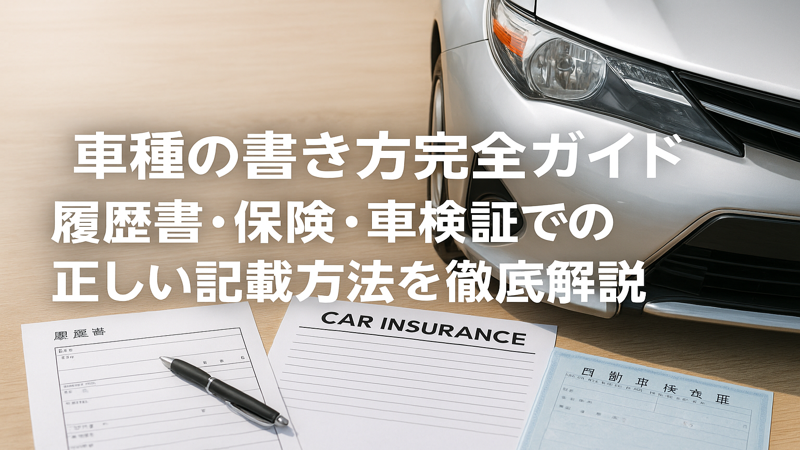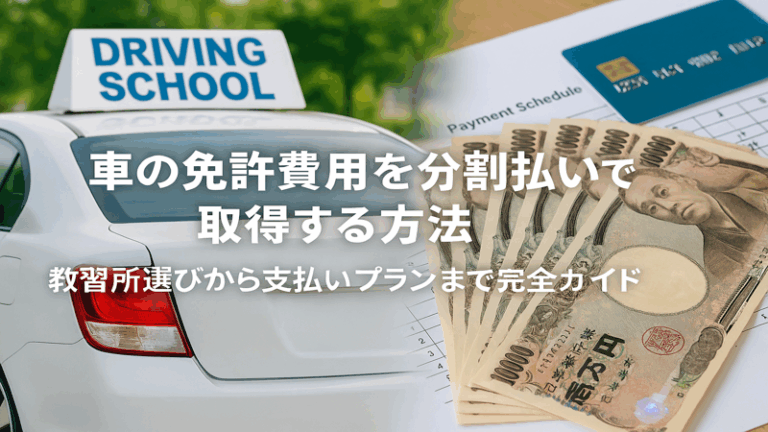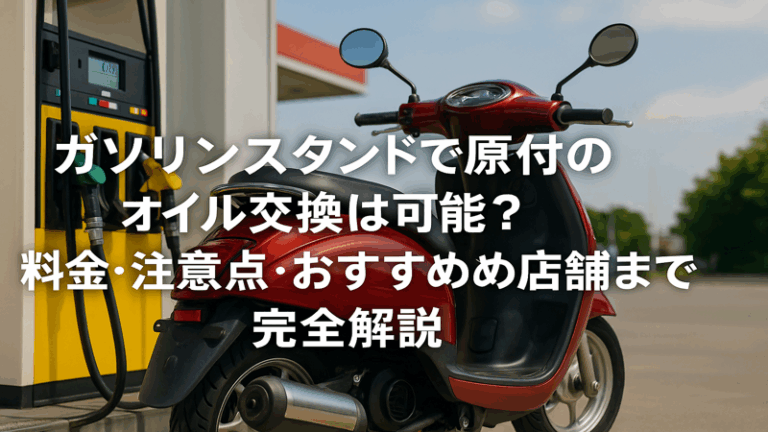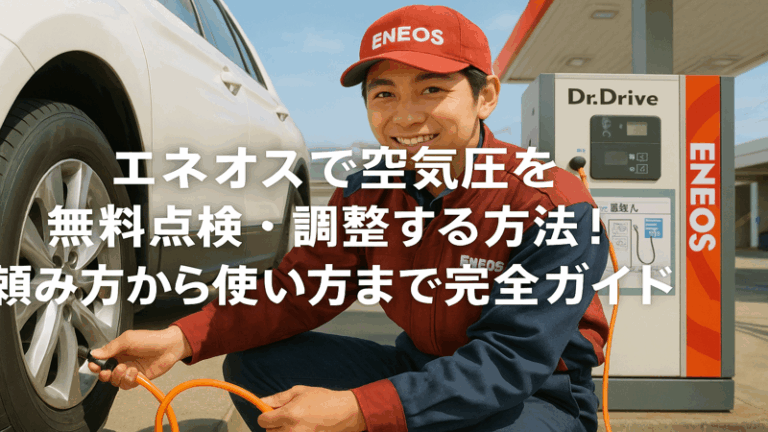車種の書き方完全ガイド|履歴書・保険・車検証での正しい記載方法を徹底解説
あなたは「車種ってどう書けばいいの?」と思ったことはありませんか?結論、車種の書き方は使用する場面によって大きく異なります。この記事を読むことで履歴書・保険・車検証での正しい車種記載方法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
1.車種とは何か?車名との違いを理解する

車種の基本的な定義と分類方法
車種とは、自動車の「種類」を表す分類のことです。
一般的に車種は、車体の形状やエンジンの大きさ、搭載されている装備などによって分類されます。具体的には、軽自動車、コンパクトカー、SUV、セダン、ミニバンなどのボディタイプによる分類や、道路運送車両法に基づく法的な区分があります。
法的な車種区分では、普通乗用車、小型乗用車、軽四輪乗用車、原動機付自転車などに分類されます。これらの区分は、車両の大きさや排気量、用途によって決められており、税金や保険料の計算にも使用されています。
自動車業界では販売戦略上の観点から、ボディタイプによる車種分類が重要視されています。一方、保険業界ではリスク評価と保険料設定のために、より細かな車種区分が使用されているのが特徴です。
車名と車種の明確な違い
車名とは、自動車メーカーが独自に考案した車個別の固有名称のことです。
例えば、トヨタの「プリウス」や「アルファード」、日産の「セレナ」や「リーフ」、ホンダの「N-BOX」や「ヴェゼル」などが車名にあたります。これらは各メーカーが商品として販売するために付けた名前であり、車の識別を目的としています。
一方、車種は車名よりも大きな概念で、複数の車名を包含する分類です。車名が「個人名」だとすれば、車種は「職業」のような関係と考えると分かりやすいでしょう。
日常会話では車名のことを車種と呼ぶことも多くありますが、公的な書類や保険契約では明確に区別されるため、正確な理解が重要です。特に自動車保険の契約時には、この違いを理解していないと適切な手続きができない場合があります。
業界別の車種の捉え方の違い
自動車業界における車種は、主にボディタイプや販売戦略上の分類を指します。
セダン、ハッチバック、ステーションワゴン、SUV、ミニバン、コンパクトカー、軽自動車などがこれにあたります。メーカーは消費者のライフスタイルや用途に合わせて、これらの車種を開発・販売しています。
自動車保険業界では、車種は保険料算出のための重要な区分として扱われます。
保険会社が使用する車種区分は「用途車種」と呼ばれ、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車などに分類されます。これらの区分により事故リスクや修理費用が評価され、保険料が決定されるのです。
また、カーリース会社などでは「国産乗用車全車種取り扱い」という表現で車名(モデル名)を指すこともあり、文脈によって意味が変わる点に注意が必要です。
車検証での車種・車名の記載場所
車検証では「自動車の種別」欄に車種が、「車名」欄にメーカー名が記載されています。
車検証の車種欄には、普通、小型、軽自動車、大型特殊などの法的な区分が記載されます。これは道路運送車両法に基づく分類であり、車検時の手数料や税金の計算に使用されます。
車名欄にはトヨタ、日産、ホンダなどのメーカー名が記載されており、一般的にイメージする「プリウス」や「セレナ」といった車名は記載されていません。
2023年1月以降に交付される車検証は電子化されており、詳細な情報はICタグに格納されています。従来の紙の車検証とは異なり、基礎的な情報のみが券面に記載され、その他の情報は専用アプリや機器で確認する必要があります。
2.履歴書における車種の正しい書き方

履歴書での車種記載の基本ルール
履歴書では車種欄に「メーカー名・車名」を記載するのが一般的です。
多くの企業の履歴書フォーマットでは「車種」という項目がありますが、この場合は法的な車種分類ではなく、具体的な車の情報を求めています。例えば「トヨタ・プリウス」「日産・セレナ」「ホンダ・N-BOX」といった形で記載します。
記載する際は車検証の情報を必ず確認しましょう。
車検証には正確なメーカー名が記載されており、一般的な呼び方と異なる場合があります。また、年式や型式も併せて記載を求められる場合があるため、事前に車検証を準備しておくことが重要です。
履歴書への記載は正確性が求められるため、曖昧な記憶に頼らず、必ず車検証を参照して正確な情報を記載してください。
運転免許証の車種記載との違い
運転免許証には運転可能な車両の種類が記載されており、履歴書の車種記載とは全く異なる概念です。
運転免許証の車種欄には「普通自動車第一種運転免許」「準中型自動車運転免許」「大型自動車運転免許」などの免許の種類が記載されます。これらは運転可能な車両の大きさや用途を示すものです。
履歴書の免許・資格欄に運転免許を記載する場合は、必ず正式名称で記載します。
「普通免許」ではなく「普通自動車第一種運転免許」と書き、AT限定の場合は「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記載します。取得年月も正確に記載し、他の項目と年号の表記方法を統一することが大切です。
通勤届での車種記載方法
通勤届の車種欄には、一般的に「メーカー名・車名」を記載します。
会社によって通勤申請書の形式は異なりますが、多くの場合「車種」と記載されている欄には具体的な車の情報を求められます。「トヨタ・プリウス」「スズキ・アルト」「ホンダ・N-VAN」といった形で記載するのが一般的です。
詳細な項目がある場合は指示に従って記入します。
「車種(車の区分)」「型式」「登録番号」「車種・車名」などの項目が設けられている場合は、それぞれに対応する情報を車検証から転記します。車種については法的な分類(自家用軽四輪乗用車など)を記載し、車名にはメーカーとモデル名を記載します。
疑問がある場合は就業規則を確認するか、人事部などの該当部署に問い合わせることをお勧めします。
3.自動車保険における車種の書き方

用途車種区分の基本知識
用途車種とは、自動車保険の保険料を算出するために必要な車種区分のことです。
用途車種は「用途」と「車種」の組み合わせで構成されます。用途は車の使用形態(自家用・事業用)を、車種は車の構造や大きさなどの違いを表します。この区分により保険加入の可否や保険料が決定されるため、正確な申告が必要です。
自動車保険では必ず告知事項として申告が義務付けられています。
用途車種を間違えて申告すると、事故時に保険金が支払われない可能性があります。また、保険会社によって分類方法が若干異なる場合があるため、契約時には保険会社の基準を確認することが重要です。
保険料は用途車種によって大きく変わるため、車両を購入する前に保険料への影響を確認しておくことをお勧めします。
自家用8車種の分類と記載方法
多くの保険会社では「自家用8車種」という分類を使用しています。
主な分類は以下の通りです:
- 自家用普通乗用車:3ナンバーの大型乗用車(プリウス、ハリアーなど)
- 自家用小型乗用車:5ナンバーのコンパクトカー(フィット、ヴィッツなど)
- 自家用軽四輪乗用車:軽自動車(N-BOX、タントなど)
- 自家用小型貨物車:小型トラック・バン
- 自家用軽四輪貨物車:軽トラック・軽バン
- 自家用普通貨物車:大型トラック
- 自家用二輪自動車:125cc超のバイク
- 原動機付自転車:125cc以下の原付・小型バイク
保険契約時には、これらの分類に基づいて正確に申告する必要があります。分類を間違えると保険料に大きな差が生じるため、車検証を参照して確実に確認しましょう。
ナンバープレートによる車種の見分け方
ナンバープレートの分類番号から車種を判別できます。
分類番号は地名の右側にある3桁の数字で、車種を示しています:
- 300番台:普通乗用車(3ナンバー)
- 500番台:小型乗用車(5ナンバー)
- 400・600番台:小型貨物車
- 100番台:普通貨物車
- 800番台:特種用途自動車
- 700番台:小型特殊自動車
軽自動車は軽自動車検査協会が管轄するため、ナンバープレートの色や形状が異なります。黄色いナンバープレートが軽乗用車、黒色が軽貨物車を示しています。
この分類番号を知っていると、保険契約時や事故時の相手車両の種類を素早く判断できるため便利です。
型式別料率クラスと車種の関係
型式別料率クラスは、車種よりもさらに細かい単位で保険料を決定する制度です。
同じ車種でも型式(年式やグレード)によって事故率や修理費用が異なるため、型式ごとに1~17段階(軽自動車は1~3段階)のクラスが設定されています。クラスが高いほど保険料も高くなります。
「対人賠償」「対物賠償」「傷害」「車両保険」の4項目それぞれにクラスが設定されており、車種選びの際の重要な判断材料となります。
例えば、スポーツカーや高級車は事故率や修理費用が高い傾向にあるため、料率クラスも高く設定されています。車を購入する前に型式別料率クラスを確認することで、将来の保険料負担を予測できます。
4.車検証での車種記載の見方と活用法

車検証の車種欄の正しい読み方
車検証の「自動車の種別」欄が法的な車種を示しています。
この欄には「普通」「小型」「軽自動車」「大型特殊」などの記載があり、道路運送車両法に基づく分類を表しています。これらの情報は車検手数料や自動車税の計算に使用されるため、正確な理解が必要です。
「用途」欄には「乗用」「貨物」「乗合」「特種」などが記載され、車両の使用目的を示しています。
「自家用・事業用の別」欄では使用形態が区分されており、これらの情報を組み合わせることで正確な用途車種が判明します。保険契約時にはこれらの情報をすべて確認して申告する必要があります。
車検証を見る際は、これらの項目の位置を把握しておくと、必要な情報を素早く見つけることができます。
電子車検証での車種情報の確認方法
2023年1月以降の電子車検証では、詳細情報がICタグに格納されています。
電子車検証はA6サイズと小型化され、券面には基礎的な情報のみが記載されています。車種などの詳細な情報を確認するには、「車検証閲覧アプリ」をスマートフォンにインストールし、ICタグを読み取る必要があります。
Android端末のスマートフォンやタブレット、ICカードリーダーでICタグの情報を読み取ることができます。iPhoneでは現在のところ対応していないため、注意が必要です。
電子車検証の移行期間中(2027年12月末まで)は、「自動車検査証記録事項」という紙の書類も併せて交付されるため、この書類で詳細情報を確認することも可能です。
車種情報から分かる車両の詳細
車種情報を正しく読み取ることで、車両の特性や法的地位を把握できます。
車検証の車種欄から、その車両が普通車なのか軽自動車なのか、乗用車なのか貨物車なのかが分かります。これにより適用される法規制や税額、保険料の概算を知ることができます。
型式情報と組み合わせることで、より詳細な車両特性が分かります。
型式からはエンジンの種類や排気量、駆動方式、年式などが特定でき、部品の適合性確認や中古車の価値評価にも活用できます。特に中古車購入時には、車検証の情報と実車が一致しているかを必ず確認しましょう。
また、車種情報は各種手続きの基礎データとなるため、名義変更や住所変更、保険の見直しなどの際には正確な情報が必要不可欠です。
まとめ
この記事で学んだ車種の書き方のポイントを整理すると以下の通りです:
• 車種と車名は明確に異なる概念であり、使用場面によって意味が変わる
• 履歴書や通勤届では「メーカー名・車名」を記載するのが一般的
• 自動車保険では用途車種区分に基づいた正確な申告が必要
• 車検証の「自動車の種別」欄が法的な車種を示している
• ナンバープレートの分類番号から車種の判別が可能
• 電子車検証では専用アプリでICタグを読み取って詳細確認
• 型式別料率クラスにより同じ車種でも保険料が異なる
• 車種情報は各種手続きの基礎データとして重要
• 記載時は必ず車検証を参照して正確な情報を確認する
車種の書き方を正しく理解することで、履歴書作成から保険契約まで、様々な場面でスムーズな手続きができるようになります。今後車に関する書類を作成する際は、ぜひこの知識を活用してください。